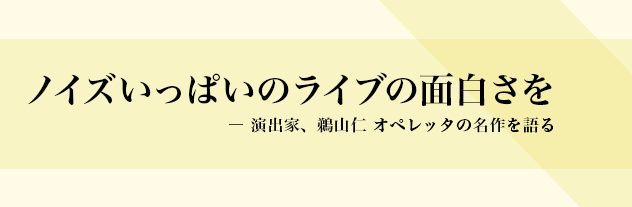演劇ライター 大原薫
大胆な劇空間を操りながら、人間の心情の機微を細やかに、時には苛烈に描き出す演出家、鵜山仁。読売演劇大賞・大賞最優秀作品賞および最優秀演出家賞・芸術選奨文部科学大臣賞を受賞した『ヘンリー六世』をはじめとするシェイクスピア劇や井上ひさし作品(『父と暮せば』『円生と志ん生』)、ミュージカル(『二都物語』)等、多岐にわたる舞台を手掛ける。

2006年の東京二期会公演『ラ・ボエーム』より。装置:島次郎 写真:高嶋ちぐさ
この三月には「ミュージカル界のプリンス」井上芳雄主演のストレートプレイ『十二番目の天使』を演出した。「妻と子供を交通事故で亡くし、人生に絶望した男性(井上)が少年野球チームで懸命にプレイを続ける少年と出会って、生きる意味を再び取り戻すというオグ・マンディーノのベストセラー小説を舞台化。モノローグを多用する独特の脚本で「芝居というのは本質的に対話で成り立っているもの。そのエネルギーを逃さないように芝居を作り上げるには難易度が高かったが、チャレンジし甲斐があった」と振り返る。
「この作品に限らず、台本というのは平面的なものだけれど、3次元、4次元に組み立て直すときにいろんなノイズが入ってくる。演技者の肉声やお客様の空気感などいろんなものが合わさって、2次元で書かれたものとは違うものができるのがライブの面白さ。そこを際立たせる演出をしたいと思っていますね」
オペラは既に出来上がっているスコアがある中で上演されるもの。これをいかにライブなものにしていくのかが、鵜山の手腕の見せどころだろう。
「オペラもライブですから、そのつど新しいリズムやフレーズを作っていかないといけない。僕が演出するときは早い話、『もっと新しい表情が見たい』『新しい声が聴きたい』。これだけなんですよ。お客様が覚えて帰ってくださるのはそういうものなんじゃないかと思うんです」
鵜山のオペラの原体験は小学校一、二年生の頃に遡る。ピアノ教師をやっていた伯母が出演するオペラコンサートに連れていかれた時のことだ。
「ヒラヒラした服を着た女の人が大勢出てきて歌うんですけど、どう考えても自然じゃないし、『これは何なんだ?』と子供心に恐ろしくてね(笑)。でも、ライブの体験って、そういう恐ろしさが病みつきになるところがあるじゃないですか。あれ以来、得体のしれない魔力に憑りつかれたのかもしれない」
歌うと人が変わる。音楽が人を狂わせる。鵜山の原体験は『天国と地獄』が描く世界に通じるものがあるようだ。
「『音楽は人を変える』というところからアプローチしていくと、ダイナミックな『天国と地獄』になるのではないかと思います」
『天国と地獄』は、ギリシャ悲劇のストーリーがパロディとなって描かれる。
「つい先日も演劇学校でギリシャ悲劇のアンソロジーを演出したんですが、ギリシャ悲劇の時代も今も、悩むところや感動するところは全然変わっていない。そもそも一つの細胞が二つに分かれた時にすでにドラマが始まっているという感覚でとらえると、2500年くらいでは人間は変わらないなと思うんです。変わらない人間のエネルギーの根源をうまく引き出せればと思いますね。『天国と地獄』では悪人と善人が出てくるけれど、そのどちらが欠けても世の中は面白くない。僕なんかはいい人ばっかりになったら死にたくなるんです(笑)。言うならば、舞台の登場人物にはワクチンのような効果があるんですよ。舞台の登場人物を見て免疫をつけてもらえたら、実生活で多少面倒なことが起きても対応できるんじゃないでしょうか」
とはいえ、『天国と地獄』初演から約150年。時代の変化を考えて、台本やスコアにアレンジを加えるところはあるのだろうか。
「『天国と地獄』の台詞はとても骨太。そこにことさら新しいアイテムを持ち込まなくても大丈夫じゃないかなと思うんです。ただ、台詞のやり取りに関わるところは、稽古の現場で、ライブの関係性から新しく生まれるものがあったら、臆せずに取り入れていきたい」

鵜山氏演出による演劇作品の舞台。2017年『鼻』(別役実 作)
写真:宮川舞子/写真提供:文学座

今年3月に東京・日比谷のシアタークリエで上演された鵜山仁演出
『十二番目の天使』の稽古風景。中央左が鵜山氏。
写真提供:東宝演劇部
鵜山仁 Hitoshi Uyama
演出家、文学座演出部所属。1953年、奈良県生まれ。慶應義塾大学文学部仏文科卒業。舞台芸術学院をへて文学座附属演劇研究所入所。82年に座員となり『プラハ1975』などを手がける。89年、『雪やこんこん』他で芸術選奨文部大臣新人賞、2004年、『兄おとうと』他で読売演劇大賞の大賞・最優秀演出家賞、10年と16年にも読売演劇大賞・最優秀演出家賞、10年には第60回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。近年の舞台に『マンザナわが町』『女中たち』『Taking Sides』など。