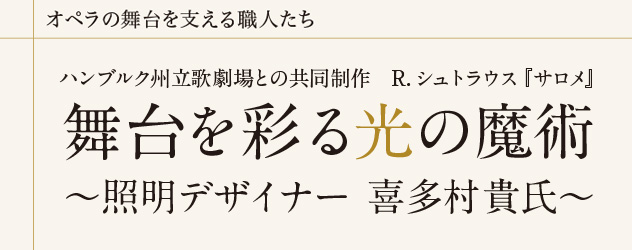海外の劇場との共同制作の演目では、毎回斬新な舞台美術も話題だ。その視覚的美しさを陰で支える照明技術は、なかなか紹介されることのない分野でもある。
6月に東京で上演される『サロメ』で、美しい光のデザインを見せてくれるハンス・トェルステデ氏とともに、東京二期会の国内上演の舞台の多くで日本側の照明コーディネーターを務めるオペラ照明の第一人者、喜多村貴氏に話を聞いた。

6月に東京で上演される『サロメ』より。
©Brinkhoff-Moegenburg/ハンブルク州立歌劇場
照明一筋40年
―オペラの照明という仕事に出合ったきっかけは?
喜多村(以下K) 青年時代から舞台芸術が好きだったのですが、まさか演じる側をやる訳にはいかず、でも何らかのかたちで作品と関われたら…、という思いがあったんですね。それで、なぜかその時、〝照明ってイイな〟と思ったんですよね。
その後、学校卒業後に今も所属している劇光社に入りました。でも、一年も経たないうちに〝もう辞めようかな…〟なんて思っていたところに、1981年のミラノ・スカラ座の引っ越し公演がありましてね、これが本当にエキサイティングでした。ゼッフィレッリの『ラ・ボエーム』。三幕のオンフェールの門に雪が降るシーンなんか、中で仕事をしながら見ていると、〝なんだ汚いモノをたくさん積み重ねて…〟なんて思っていたんですが、いざ本番で正面から見たら、夜空に舞い落ちるひとひらの雪が照明に映える美しさに感動したんです。

1981年ミラノ・スカラ座公演『ラ・ボエーム』の第三幕、喜多村さんが当時感動した雪の舞い落ちるシーン。
写真提供:NBS/公益財団法人日本舞台芸術振興会
ハンス・マジックふたたび
―6月の東京二期会『サロメ』には、喜多村さんはどのようなかたちで関わるのでしょうか。
K 二期会さんの公演で、二度一緒に仕事をしているドイツ人照明デザイナーのハンス・トェルステデさんとともに、私は日本側の照明コーディネーターとして、彼らのイメージを日本の舞台仕様に合わせていくことになると思います。ハンスさんは、2016年の『トリスタンとイゾルデ』同様に演出家のヴィリー・デッカーさんと組んでいて、彼ら二人のコンセプトに加え、装置・美術家の意見を汲んで我々が調整して、具体化していくかたちです。
―喜多村さんの目から見て、ハンス・トェルステデ氏の照明デザインは、どのような点が特徴的なのでしょうか。
K ハンスさんの持ってくるイメージは、ドイツ人らしく緻密に作り込んであり、演出家の意図するところを見事に引き立たせています。文字通り、演出家のイメージに色を付け、付加価値を与える。色彩にしても、何を突出させるわけではないのですが、全体像のバランスが際立っています。かと言って、一つひとつのシーンも完璧に美しく、それこそが彼流のマジックだと感じています。

『サロメ』で照明を担当するハンス・トェルステデ氏によるメトロポリタン歌劇場上演作品『椿姫』の舞台より。3/8~14『カルメン』、4/12~18『連隊の娘』他、上映予定。詳しくはhttps://www.shochiku.co.jp/met/ にて。 ©Ken Howard/Metropolitan Opera

『サロメ』でも再び登場するヴィリー・デッカー演出による東京二期会『トリスタンとイゾルデ』より。ハンス・トェルステデ氏による照明デザイン。 ©三枝近志
照明の仕事とは…
―海外の照明技術者と日本のそれでは、仕事のプロセスやイメージに違いはありますか?
K 海外では、照明チームは演出家の絵コンテを基に抽象的なイメージや色をざっくりと提案するだけです。音楽的なことは演出助手などがアシストしてくれますし、あとは周りのクリエイティブ部隊がそれぞれに動くという〝流れ作業〟がしっかり固まっています。一方、日本では、現場に入れば、「まず音楽ありき」というのが大前提で、照明チームと言えども、譜面をしっかり追いながら、毎回稽古場で人物の動線や空間のイメージなどを物理的に捉え、計算しながら尺ごと(あるまとまった小節の単位)に照明変化の指示を書き込んでいくんですね。音楽や役の立ち回りを加味しての一連の作業をすべて照明チームでカバーしています。
―40年近いキャリアの中で、喜多村さんはオペラ演出の進化や変遷などもしっかりご覧になっているわけですね。
K はは、そうですね。僕たちは若い時からオーソドックスな舞台をたくさん見てきているので、近年コンセプト主導の舞台を目の当たりにした時も、〝おお、こう来たか。こうなるんだぁ〟、〝これは面白い!〟と意外とすんなりと受け入れられたんです(笑)。職人的にみれば、オーソドックスな舞台では、照明というのは時のうつろいを表し、舞台をより美しく見せるというところに着眼点がありましたが、新しいタイプの舞台では、時間経過や空間自体の存在はむしろ重要視されることなく、演出家のコンセプトにドーンと肉薄していく面白さがありますよね。
―ちなみに次代を担う後継者についてはいかがですか?
K はは、これがなかなか難しくて。照明に限らず舞台の裏方は、美術・装置なんかもみんな40年変わらないメンバーでやってますね(笑)。その中でも比較的若いメンバーは、実は男性よりも女性のほうが長く活躍してくれています。ぜひ若い方にもオペラの照明という分野の仕事の面白さを知って頂けたら嬉しいですね。
喜多村貴(きたむら たかし) 照明デザイナー
1981年(有)舞台照明劇光社入社。88年照明家協会新人賞。92年から東京バレエ団のチーフとして海外公演に参加。ミラノ・スカラ座、ウィーン、バイエルン、ベルリン州立歌劇場、メトロポリタン、ボローニャ各歌劇場等のオペラ、バレエ日本公演の照明チーフとして参加。東京二期会ではコンヴィチュニー演出『エフゲニー・オネーギン』『マクベス』、深作健太演出『ダナエの愛』『ローエングリン』、カロリーネ・グルーバー演出『ナクソス島のアリアドネ』、ギー・ヨーステン演出『後宮からの逃走』の照明デザインを手掛けている。