〈あらすじ〉
スペイン貴族の娘コンスタンツェは、航海中に海賊の手に落ち、従僕のペドリッロと侍女のブロンデとともに、トルコの太守セリムの手に売り渡されてしまった。異国の海辺の宮殿に囲われているコンスタンツェ。太守は美しいコンスタンツェに言い寄るが、彼女は頑として色よい返事はしない。なぜなら、彼女には故郷の恋人、ベルモンテがいるのだ。そんな中、ペドリッロは、故郷のベルモンテにこっそり救出を依頼する。
海を越え、コンスタンツェを救いに来たベルモンテ。コンスタンツェの無事を確認するものの、太守が彼女に激しく求愛し、一方で太守の番人オスミンは、ブロンデを狙っていることが分かる。
あの手この手で、ついにコンスタンツェと再会を果たすベルモンテ。脱走計画は成功したかのように見えたものの…。絶体絶命の危機に陥った二人を待ち受けていた結末は…。
『後宮からの逃走』が私たちに与えてくれるカギについて
モーツァルトの愛した異国趣味
かつてオスマン・トルコは二度にわたって大軍でウィーンを包囲し、市民を恐怖のどん底に叩き込んだ。彼らはすさまじい勢いで太鼓を鳴らしながらその威力を誇示したという。キリスト教文化圏をハプスブルク帝国が東への防壁として守り切った歴史的役割は大きかったが、この隣人は、さまざまな文化も同時に伝えてくれる有難い存在でもあった。そもそもオーケストラの楽器は、もとを正せばすべてイスラム文化圏由来という説もある。コーヒーだって、ウィーンの人たちはトルコからやってきたものを自分たちが一番最初に受け入れた、と信じている。
過去の記憶が薄らいだ18世紀になると、トルコは異国趣味の対象として好奇の目で見られるようになった。モーツァルトの書いたトルコ風の音楽のいくつかは、その反映でもある。
『後宮からの逃走』は、モーツァルトの書いたあらゆる作品のなかで、もっとも色彩感の強烈な、パワフルな音楽の一つである。各種の打楽器やピッコロの響きは、オペラ全体にはちきれんばかりのリズムの生気を与える。「トルコ行進曲付き」のピアノ・ソナタが好きな人は、『後宮からの逃走』を聴くことで、モーツァルトの考えるトルコ風がいかなるものなのか、まざまざと具体的なイメージを与えられることだろう。
時代を超えて輝く愛の力
『後宮』のテーマは、異国趣味だけではない。違う文化や宗教を持つ隣国と、いかにして付き合っていくべきか、という今日的問題をも内包している。
トルコの太守セリムの家来オスミンが象徴するのは、野蛮な衝動と怒り、残酷さと暴力への嗜好である。それだけではない。モーツァルトはオスミンに愛らしく見事な音楽をつけ、彼が愛に渇望感を覚えている男であることに理解と共感を寄せている。
それに対し、セリムはドラマに最大の影響力を行使する重要人物であるにもかかわらず、全く歌わずセリフだけしか与えられていない。だがそのことでセリムの孤独感はいっそう浮き彫りになる。最後、セリムは驚くべき寛大さを示すが、寂しげで謎めいた余韻を残す。実に魅力的な人物像である。
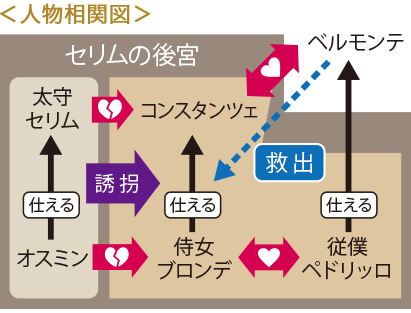
〈登場人物〉
セリム/太守(語り役) ベルモンテ/スペイン貴族
コンスタンツェ/ベルモンテの婚約者 ペドリッロ/ベルモンテの従僕
ブロンデ/コンスタンツェの侍女 オスミン/太守の後宮の番人
セリムが奴隷市場で買い求めた二人のヨーロッパ人女性、貴族の娘コンスタンツェとその侍女ブロンデは、保護される身でもある。セリムは部下のオスミンにブロンデを与え、自分はコンスタンツェの愛を求める。彼女たちは拒絶しながらも、少しは心の扉を開いているようにも思える。果たして彼女たちは本来の恋人たち?ベルモンテと従僕ペドリッロのために、操を守ったのだろうか?いや、口では操と言いながらも、彼女たちの心はそんな堅苦しい道徳観念によって動いているわけではない。ブロンデは乱暴者のオスミンに向かって、こんな意味のことを歌う。
「もし女の心を惹こうと思ったら、怒鳴ったり命令したりするのはやめて。細やかな愛情と優しさと親切、そしてユーモア。女の心を惹くにはそれが一番なの。女は男に与えられる贈り物なんかじゃない。奴隷でもない。たとえ誰かに束縛されていようとも、伯爵夫人のように私の心は自由に生きられるのよ」
セリムの脅しと怒りに対する、コンスタンツェの抗弁はこういう意味だ。
「あらゆる拷問が待ち受けていようとも、私は苦痛に耐えて見せましょう。私は一人の女として筋を通し、女としての尊厳を守りたいのです。もし私を罰したければ、私が死ぬまでそうなさればいいでしょう。私を暴力で殺すか、さもなくば寛大なお心を。二つに一つをお選びください」
ここで歌われるコンスタンツェの大アリアは、歌詞をそのまま表面的に鵜呑みにして、ただの「私は操を守ります」という道徳的な歌と思ってはいけない。暴力か、寛大さか、二つに一つを選ぶなら、あなたはどちらを選ぶのですか?という命がけの訴えにほかならない。
コンスタンツェの全存在をかけたこの大アリアが、いかにオペラ全体を照らし出しているか。まるで大交響曲のひとつの楽章のように力強く輝き、時代を超えてこの世界を崇高に照らし出しているか。その意味は暴力への抵抗と、愛と寛大さを求めるモーツァルトからの、聴き手に向けた心からのメッセージでもある。
悪には悪で報いるべきだろうか? 憎しみには憎しみで? たしかにいまはそういう時代かもしれない。それが現実なのだろう。だが、『後宮』のラストシーンでセリムの口から発せられる言葉は、こう語っている。
「復讐ほどむごいものはない。悪や憎しみに対抗しうるのは、温かさ、優しさ、寛大さ、そして善行である。このことがわからない者は、軽蔑に値するのだ」
異国趣味の愉悦に満ちた生き生きした音楽が、愛のドラマとともに私たちを連れて行ってくれるのは、善なるものがもう一度輝きを取り戻す、こうした地点である。

右)1800-1850年代、ドイツの劇場で上演された際のコンスタンツェ、カロリーネ・フィッシャー・アハテン
左)フアン・ヒメネス・マーティン(1855-1901)≪ハーレムで≫
画像出典:Wikimedia Commons
『後宮』~モーツァルトのオペラを知るカギ~
『後宮』の登場人物たちには、モーツァルトのその後のオペラの萌芽が、たくさん詰まっている。『魔笛』や『コシ・ファン・トゥッテ』を楽しむときに、『後宮』を知っていることが、どれほど聴き方に奥行きを与えてくれることだろう。セリムは威厳に満ちたザラストロの原型であり、ベルモンテは王子タミーノ、ペドリッロは楽天家パパゲーノに似ている。悲しみのコンスタンツェはパミーナでありフィオルディリージでもあるだろう。ブロンデの色気はドラベッラやデスピーナに通じる。オスミンのキャラクターは愛を乱暴に求めるモノスタトスに通じる。
有名な「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」の第二楽章にそっくりな瞬間も出てくる。ベルモンテが歌うアリア「嬉し涙が落ちるとき」の歌いだしがそれだ。そこで語られているのは、「恋する男にとって愛する女性を抱きしめ、口づけする喜びはどんな栄華や王冠よりも尊い」という意味である。つまり男にとってキスとは何かということである。それを知っていれば、あの名曲がどれほど違って聴こえてくることだろう。
ウィーンで活躍を始めたモーツァルトが意欲満々で書き上げた『後宮』は、その後の傑作群の扉を開くためのカギを聴き手に与えてくれる、そんな作品でもある。
文・林田直樹(音楽ジャーナリスト・評論家)






