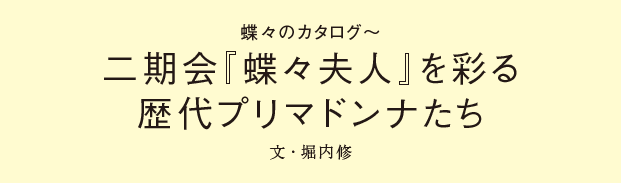死んだ蝶々さんの数を数える。これは大変につらい作業……ではなくて愉しい作業だ。悲劇のヒロインは自害するが、再び幕が上がるとにこやかに微笑んでくれるからだ。笑顔のヒロインを何人も思い出すのは甘美な作業に決っている。
だがこれまで蝶々さんを歌ったソプラノを思い出そうとして、困ったことに気づいた。「蝶々さんを歌ったソプラノ」ではなく、「ソプラノが歌った蝶々さん」を思い出してしまうのだ。きっとそれこそが二期会の誇るべき『蝶々夫人』の証しなのだろう。これまで聴いたソプラノたちの誰ひとり本物の蝶々さんにならなかった人はいなかったのだ。
1957年、日比谷公会堂での上演は、子供のころだったから聴いていない。最初の、そして特に印象的な二期会の『蝶々夫人』は、日生劇場での三谷礼二演出の上演だった。傘がくるくると回り、蝶々さんの強い想いが見事に描かれた、あの上演だ。阿部容子、高木鳩子の二人が蝶々さんを歌った。風車の回る「愛の二重唱」でまろやかな声を聴いたのは阿部容子だったと思う。
プッチーニ作のイタリア・オペラだから、日本が『蝶々夫人』の本場ってことはないのだけれど、蝶々さんに関しては本場かもしれない。思い出すうちにそんな気になってくる。
初演と改訂版初演で歌ったソプラノが違っていたせいか、蝶々さんはドラマティックとリリック、あるいは情熱的な女とかわいい女の、どちらのタイプも歌い、舞台でせめぎ合っているといわれる。日本人ソプラノは後者の典型で、ひとつの流れを作ってきた。その通りなのかなと、二期会の蝶々さんたちを振り返ると、信じたくなる。
藤沢で歌った岩崎由紀子はまさに「かわいい女」の蝶々さんという印象だった。だがいまから思えば、その時が二期会純正というべき栗山昌良演出『蝶々夫人』の最初の体験だったのも大きかったに違いない。確かにその時の岩崎由紀子は、姿も声も「古い日本の女」だったのだが、すでにここで栗山昌良の、そして二期会の『蝶々夫人』が形成されていたのだ。

毛利純子(1957年)

阿部容子(1977年)
ずいぶん前のことなので定かではないのだが、1984年日生劇場での片岡啓子の蝶々さんは、必ずしも「かわいい女」タイプではなかったのではないかと思う。断固として待ち、意志を貫いて自害する女の面が強められた歌ではなかったろうか。それでも、けなげな、かわいい蝶々さんになったから、蝶々さんは歌うソプラノだけのものでなく、演奏や演出によって作られる面もあるのだろう。
もうひとつの、つまり三谷礼二演出による『蝶々夫人』が1990年に、大野和士の指揮で上演されている。島崎智子の、これが二期会デビューだった蝶々さんは、歌えて動ける蝶々さんとして話題になったのではなかったろうか。なんというか、ちっともおとなしくない蝶々さんだった。

片岡啓子(1984年)

島崎智子(1990年)
おとなしくないといえば、その後代表的な蝶々さんのソプラノとなった木下美穂子が二期会の『蝶々夫人』に登場したのは、2003年の上演だった。すでに上演は字幕付原語上演の時代に入っていた。日本語よりも原語、つまりイタリア語のほうが、遠慮なく感情表現ができるのか、それともイタリアで学んだ歌手たちには歌い易いのだろうか。
栗山昌良の演出が続き、続くだけでなく、回を重ねるごとに徹底していったので、日本の女の一種の理想像としての蝶々さん像が、ますます鮮明になってゆくのだが、一方で蝶々さんの感情表現も露わになってゆく。木下美穂子はその典型なのではないか。蝶々さんはあくまでしとやかな古い日本の女で、所作にぬかりはないが、一方で自分の意志を貫く強い女の面も成長させてゆく。時代の変化が舞台にというより、蝶々さん自身に反映しているのだろう。
栗山演出『蝶々夫人』は二期会の定番になり、2003年からは3年ごとに上演されている。06年と09年には大山亜紀子が歌っている。もう一昔前の日本のソプラノが歌う蝶々さんはこういうタイプ、という分類の時代は終ってしまったのではないだろうか。

木下美穂子(2003年)

大山亜紀子(2006年)
昔ウィーンの歌劇場に東敦子が蝶々さんとして出演した時、第1幕でピンカートンが蝶々さんを軽々と抱き上げて寝室に入り、聴衆を驚かせたことがあった。やっぱり蝶々さんは日本のソプラノにぴったりの役か、と思われたのだが、もう過去の話になった。二期会の蝶々さんはかわいい女路線を堅持しつつ、自分の歌でピンカートンの乗る船を出現させるくらいの強さだって、発揮するようになっている。
残念ながら聞き逃してしまった二期会の蝶々さんが何人もいるのだが、聴いてきたソプラノを思い出すだけでも晴れやかな気分になる。舞台で死んだ蝶々さんはよみがえり、成長を重ねている。さあ、カタログにもうひとり、いやふたりを加えることにしよう。大村博美と森谷真理なのだから、とびきりの1ページになるはずだ。

栗山昌良と佐藤功太郎