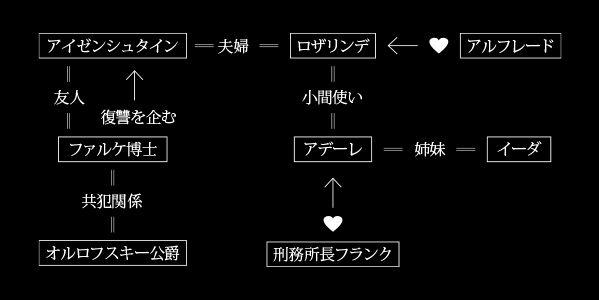ウィーンの光と影
本当ならば、タイトルは「ウィーンの『こうもり』……」と書いたほうがよいかもしれない。『こうもり』は、ウィーン子のヨハン・シュトラウス(1825~99)が、自分の生きているリアルタイムのウィーンを描いてみせたオペレッタだからだ。
『こうもり』が生まれたのは、1874年のこと。当時のウィーンの人々は、前の年に起きた2つの出来事の記憶を忘れられないでいた。1つ目はウィーン万国博覧会。この街の象徴ともいえる大公園のプラーターを会場に、世界各地から人々が集まってきた。
おりしも当時のウィーンでは、中世以来の古い市壁が取り壊され、その跡地に新しい環状道路が開通したばかり。モダンなガス灯がともり、路面鉄道馬車が行き来し、さらに環状道路の両側には宮廷歌劇場などの文化施設、行政施設をはじめ、高級マンションや高級ホテルが立ち並んだ。そして、このような新生ウィーンの総仕上げとして開催されたのが万国博覧会だった。
ところが博覧会が開催される直前になって、ウィーンの下町でコレラが発生する。当局はやっきになって否定したものの、何やら不吉な前兆だった。そして果たせるかな、博覧会が開幕して数日後、今度は株が大暴落した。近代都市ウィーンを造ろうという掛け声の下、この街は数年来、大投機ブームに湧いてきたのだが……シュトラウスもこのブームに乗って財テクをしていた1人だった……、そこへ冷水が浴びせられた。一瞬にして紙屑同然となった証券を投げ捨て、自殺した投資家も少なくなかった。
酔い心地で憂いを忘れて…
そんな光も影もあるウィーンの世相の只中に生きていたシュトラウスが書いたのが、オペレッタ『こうもり』だ。
元々オペレッタは、肩の凝らない華やかなミニオペラといった意味合いで、パリで19世紀半ばに人気を博し、ヨーロッパ中に広まった。それに刺激を受けて、ウィーンでもオペレッタを……という動きが高まる中で、シュトラウスもそのブームに乗る。といってもパリのオペレッタが、向かうところ敵なしの成長を遂げていたフランス社会を軽妙に風刺しているのに比べ、ウィーンのそれは、数百年にわたる繁栄の末に落日の時を迎えつつあったオーストリアの抱える深い憂いを掬い上げる。
『こうもり』も例外ではない。第1幕の後半、恋のアバンチュールに密かに惹かれている美しい人妻のもとを、間男が訪ねてくるシーン。口先では浮気を拒否してみせる彼女の本心を見透かして、間男は次のように囁きかける。「忘れられればそれで幸せ どうせ人生変えられないんだから……。」見方を変えればそれは、突然の恐慌によって成長への夢を絶たれた当時のウィーンの人々へ向けられたメッセージではなかったか?
しかもこのメッセージ、咽び泣くようなスローワルツに乗せて歌われる。さらに禁断の恋を内緒で楽しもうとしている2人の手に握られているのは、……台本によれば……ハンガリー名産のねっとりとしたトカイワイン。人間の力でどうにもできない状況が訪れた時には、逆に甘い酔いに任せて一瞬なりとも辛さを忘れてしまおうという、シュトラウスならではのほろ苦い知恵が滲み出ている。


©Monika Rittershaus
ウィーンvsベルリン
実のところシュトラウスがこのような知恵を発揮したのは、『こうもり』が最初ではない。遡ること数年前の1867年、彼は男声合唱団とオーケストラのためのワルツを作曲したのだが、その歌詞は次のようだった。「陽気にゆこうぜウィーンのみんな/へえ 何で?……苦しんでも嘆いても仕方ないのなら 楽しく陽気にやろうぜ!」
少し説明が必要だろう。このワルツが誕生した前年の1866年には、ベルリンを都とする北東ドイツの新興国家プロイセン王国に対してオーストリアが戦火を交え、あっけなく敗北するという衝撃的な事件が起きたばかりだった。もちろんウィーンも、敗戦ムードに沈む。そんなウィーン子を励ますためにシュトラウスが作ったのが、上のワルツなのだ。
その題名こそ、「美しく青きドナウ」。「オーストリア第二の国歌」と呼ばれる超有名曲で、今では合唱を抜いたオーケストラだけのバージョンのほうが有名だ(なおこのバージョンはウィーン万国博覧会の開幕式典でも、シュトラウス自身の指揮によって演奏されている)。
いずれにしても、オーストリアにとってプロイセンとは、……同じドイツ語を喋る地域であるにもかかわらず……わだかまりのある相手だった。それぞれの首都の気質を見ても、万事においてかっちりとしたベルリンと、深刻な事態を丸く受け流そうとするウィーンでは、水と油の関係といってもよい。
にもかかわらず今回は、ウィーンに生まれた『こうもり』をベルリンのオペラハウスが扱ったプロダクションが東京で実現される。過去の対立を超えた融合が果たされる。
兄弟姉妹となる瞬間
対立を超えた融合……。これは『こうもり』の隠れたテーマの1つだ。
たとえば第2幕のパーティのシーン。招待客は、皆が皆、名前と身分を偽って会場に集まってくるといういわばリアルな仮装舞踏会なのだが、ワルツやポルカの陽気なダンス音楽をバックに振舞われるシャンパンの酔いにまかせて、誰も小さなことなど詮索しなくなる。つまりそこには、日常生活では当たり前の敵味方も上下関係も存在しない。
その結果、何が起こるか?パーティに集う全員が兄弟姉妹となり、情熱的なキスを交わし合う。一瞬のことかもしれないが、ベートーヴェンが「第九」で示した兄弟愛の世界が、しかもベートーヴェンのような生真面目さではなく、退廃的な香りも濃厚に漂う官能の中に成就する。それまで笑いに包まれていた舞台が、楽しさはそのままに、突然崇高な輝きに満ちる場面だ。
もちろんそうなるためには、ヨーロッパ長年の伝統と格式に裏打ちされたパーティの情景が繰り広げられなければならない。さらには、音楽と音楽の間に挟まれるユーモアとウィットに富んだ会話が理解できないと魅力半減というもの。だがこの『こうもり』では、ベルリン仕込みの粋な演出を背景に、歌唱はオリジナルのドイツ語、台詞は日本語の特別バージョンが披露される。
こうして、ベルリンの『こうもり』が東京に舞い降りようとしている。ちなみにこの作品誕生のきっかけを作った1873年のウィーン万博は、長年の鎖国状態を脱したばかりの日本が、文化面での本格的な国際体験をおこなった、初めてのイベントだった。
文・小宮正安
オペレッタ『こうもり』とは?
主人公は倦怠期を迎えた夫婦、アイゼンシュタインとロザリンデ。アイゼンシュタインは刑務所行きが決まっているのだが、その前夜に友人のファルケ博士から、オルロフスキー公爵の夜会へ誘われる。主人の去った家に元恋人で歌手のアルフレードがやってきてロザリンデを口説き始めるが、そこに刑務所長のフランクが現れ、アルフレードをアイゼンシュタインと勘違いして連れて行く。
さて夜会では、女優に扮した小間使いのアデーレ、フランス人になりすましたフランクなど、様々な思惑を抱いた人たちが入り乱れている。アイゼンシュタインは、仮面をつけたハンガリーの貴婦人を口説き始めるが、彼女は夫の浮気をこらしめようとやってきたロザリンデの変装だった。
実はこの夜会は、以前アイゼンシュタインに「こうもり」とあだ名をつけられたファルケ博士が仕組んだ、ちょっとした復讐劇。さて、男女入り乱れてのドタバタ騒動、いったいどんな結末を迎えるのやら……。