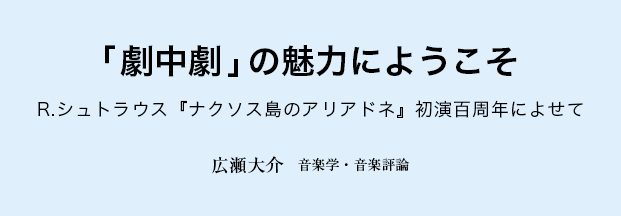突然ですが、読者の皆様は“メタ・フィクション”という言葉をご存じでしょうか。作品が属しているジャンルそのものを内側から批評しているような作品のことを指します。演劇の世界であれば“劇中劇”という言い方のほうが馴染み深いでしょうか。
古典作品であれば、シェイクスピア『ハムレット』の例が有名でしょう。この作品では、王の后と結婚するために王を殺す悪人を扱った“劇中劇”が演じられます。ハムレットは叔父クローディアスの動揺を見て、叔父が父を殺したことを確信する、という重要な役割がこの“劇中劇”には課せられているのです。また、最近であれば、美内すずえの名作漫画『ガラスの仮面』を挙げねばなりません。女優・北島マヤの成長物語でもある長大な作品の中では、『紅天女』をはじめとするいくつもの“劇中劇”が演じられます。演劇の世界の中に演劇が存在する入れ子構造によって物語が進行し、作品を盛り上げます。
作曲家リヒャルト・シュトラウス(1864 ~1949)と台本作家フーゴ・フォン・ホフマンスタール(1874 ~1929)による『ナクソス島のアリアドネ』も、まさにそんな“劇中劇”を持ち合わせた作品であり、オペラというジャンルについての自己言及に溢れたオペラです。交響詩や歌曲の世界で名を挙げていたシュトラウスは、『サロメ』(1905年初演、以下初演年)、『エレクトラ』(1909年)、『ばらの騎士』(1911年)などのヒット作品を立て続けに飛ばし、念願だったオペラの世界での成功をようやく手に入れました。ホフマンスタールという最高のパートナーを得たシュトラウスが、『ばらの騎士』の後に向かおうとしたのは、ふたりがそれぞれに生きている音楽と演劇の世界を結びつけた、新しい境地でした。どちらのファンにも受け容れられるような作品を作り出せば、どちらにとっても新たな可能性が開け、より広範な支持が得られる、と考えたのです。
古典作品に造詣が深く、現代風の翻案作品を書くことを得意としたホフマンスタールは、新しい作品の題材を、フランス古典主義の喜劇作品の大家、モリエール(1622~1673)の晩年の傑作『町人貴族』に求めます。貴族になろうとする俗物商人、ジュルダンが喜劇と悲劇を同時に上演するように命じ、その結果として生まれた“劇中劇”が『ナクソス島のアリアドネ』という趣向でした。
ただ、前半に演劇としての『町人貴族』(シュトラウスはその付随音楽を作曲)を置き、後半に劇中劇(これは書き下ろし)としての『アリアドネ』を置くというこの試み、1912年のシュトゥットガルトでの初演は、失敗に終わってしまいました。演劇を観に来た客は後半のオペラに、オペラを聴きに来た客は前半の演劇に飽きてしまったのです。その意味では、シュトラウスとホフマンスタールの試みは、やや時代に先走りすぎたのかもしれません。
ふたりはこの後、前半の『町人貴族』部分を、同じようなストーリーを持つ“序幕”に構成し直し、後半のオペラを改訂した上で、1916年にウィーンで再演しました。現在、とくに断りなく『ナクソス島のアリアドネ』が上演される場合は、このウィーン版を指すのが普通です(そして、今年はこの改訂版初演からちょうど百年にあたります)。この改訂によって、前半と後半がより有機的に結びつき、後半の“劇中劇”の面白さと風刺性がより際立つことになりました。

“序幕”と“オペラ”による本作の構造だけが、自己言及的な“メタ・フィクション”なのではありません。本編のオペラ(すなわち後半)だけを見ても、テセウスに棄てられた悲劇のアリアドネが酒神バッカスと新しい愛へと歩み始める“まじめな悲劇”(オペラ・セリア)パート、そしてツェルビネッタとその仲間たちが繰り広げる“ドタバタ喜劇”(オペラ・ブッファ)パートが、詩人と作曲家の鮮やかな離れ業で結びつけられます。オペラそのものも、“オペラについてのオペラ”という自己言及の形を保っているわけです。そして、ホフマンスタールが腕によりを掛けた愛への讃歌を、シュトラウスの真摯かつ華麗な音楽が高らかに歌いあげています。
演劇とオペラ、両者の要素を併せ持っているこの題材は、演出家の想像力を様々に掻き立てるようで、意欲的なプロダクションの記録が数多くのこされています。伝統的な演出ではウィーン国立歌劇場(1978年、フィリッポ・サンジュスト演出、カール・ベーム指揮)とメトロポリタン歌劇場(1988年、オットー・シェンク演出、ジェイムズ・レヴァイン指揮)が双璧と呼べるでしょう。MET&レヴァインの組み合わせでは、2003年のイライジャ・モシンスキー演出もお薦めです。グラインドボーン音楽祭(2013年、カタリーナ・トマ演出、ウラディーミル・ユロフスキ指揮)の演出は、戦争という極限の状況を取り入れることで、序幕とオペラの世界がより緊密な関係を持つことになりました。シュトゥットガルト初演版に基づいた上演では、(かなりプロダクション独自の要素が含まれてはいますが)ベヒトルフによる演出がザルツブルク音楽祭で披露されました(2012年、スヴェン=エリック・ベヒトルフ演出、ダニエル・ハーディング指揮)。音だけの録音では、初稿ではケント・ナガノ指揮、リヨン国立歌劇場管弦楽団(1997年)、改訂稿ではジュゼッペ・シノーポリ指揮、ドレスデン・シュターツカペレ(2000年)を推します。世界中でも一定の上演回数を保っている本作の魅力を、これらの映像・音源はそれぞれに伝えてくれています。
1912年シュトゥットガルトでの初演時の舞台写真
いずれもRichard-Strauss-Archiv, Garmisch所蔵
前半の演劇としての『町人貴族』の1シーン |
ツェルビネッタと愉快な道化役者たち4人の1シーン |