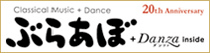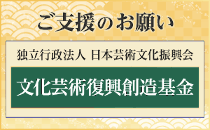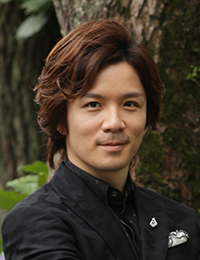photo by Taku Fukumizu
福井 敬
若き王子の悲しみと虚しさを、
声を通して表すこと
二期会の看板テノールとして、イタリア、フランス、ドイツなどさまざまな国や、作曲家、時代を超えた、幅広いレパートリーを誇る福井さんが『ドン・カルロ』に挑むのは、これが2回目。
「1999年1月にびわ湖ホールで、やはり5幕版で歌いましたが、体力的にはかなりきつかった記憶があります」
この作品は、第1幕の“フォンテーヌブローの場”を除いた4幕版での上演が多いが、今回はあえて5幕版が選ばれた。おかげで聴きどころが増えたうえに、筋書きのわかりやすさが増している。が、一方で、歌手の負担は大きい。というのも、
「カルロ役は全幕にわたって弛緩する部分がありません。いつも何かに嘆き、怒り、人間の影の部分を抱え、その状態をずっと持続している。しかも、親友のロドリーゴはフランドルの再興を画策し、フィリッポ2世はスペインのために何かをなそうとしているのに対して、カルロは運命に流され、自分では何もなせない、そういう虚しさを抱えています」
その難役に対して福井さんは、
「王子としての品位を保ちながら絶望感を出す。難しいけれどやりがいがあります」
と、抱負を語る。そもそも福井さんにとって、今年生誕200年を迎えたヴェルディは、馴染みの深い作曲家である。
「二期会やびわ湖ホールでこれまでヴェルディは13作品を歌いました。びわ湖では初期から中期の7作品を歌っています。後期の作品は、ヴェルディ自身が年を重ねるにつれ、陰影が濃くなっているようです」
そして、ヴェルディのオペラ一般をこう評する。
「イタリアオペラの中でも一番、野太い芯を持っている。人間の持つ芯の部分の強さ、弱さを感じさせる。だから、歌う際にも常に、人間の根源的な生き方を考えさせられるのです」
そこで百戦錬磨の福井さんならではの、役柄の深掘りが期待されるわけだが、それを“声”でどう描くのだろう。
「やっぱりヴェルディ作品が求める声の“色”が必要になりますね。そして、力強さだけでなく、人間の弱さ、繊細な部分を声でどう表現するか考えなければなりません」
今回はイタリア語だが、ほかにドイツ語、フランス語と、歌い分ける福井さん。そこに困難はないのだろうか。
「音域や言語の違いはありますが、私はそれを音楽やドラマの違いだと捉えます。それよりも、役柄にどう関わっていくか、カルロなら声の特質はどうで色はどうか、ということこそが重要なのです」
ベテランならではの含蓄ある言葉。もう一人のカルロ、若い山本耕平さんに対しては、
「山本さんはカルロという役柄が、年齢的にシンクロしていて、さっそうとした若々しい声と音楽の、素晴らしいカルロになると思います。逆に私は、若い王子を、声を通して形作ってみなさんにお見せしなければなりません。二人のアプローチがまったく違うので、おもしろいキャスティングだと言えますね」
若さゆえの悩みの深さは、年輪を重ねてこそ表せるものもある。それは芸術ならではの逆説だろう。
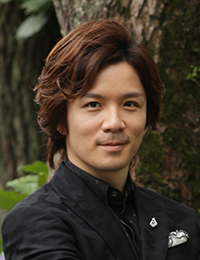
photo by Katsuaki Hirose
山本 耕平
イタリア仕込で年齢も近い、
等身大のカルロに期待!
アイドルのように端整な容姿で、いかにも王子然とした山本さんは、元来、教員志望だったという。
「中学、高校の音楽の先生が声楽専門だったので、いろいろなオペラに触れる機会がありました。吹奏楽部でもオペラを編曲したものをよく演奏していましたが、声楽は高2のとき、受験のために勉強したのが最初です。東京学芸大のクラリネット専修に入学後、東京芸大声楽科に入り直しましたが、歌に専攻を変えてからもずっと教員になるつもりでした」
その後、歌うのがどんどん面白くなったそうで、芸大の学部を卒業した年にイタリア声楽コンコルソ、翌年には日伊声楽コンコルソで第1位に入る。
「教員になったときに“コンクールでここまでいけた!”と言えるかなぁと思って」
と気負いはないが、むろん、簡単に1位が獲得できたわけではない。
「楽譜にある音を出せずに、落ち込むこともありました。でも、負けず嫌いなのでどんどんのめり込んでいきました」
2つのコンクールの賞金で2年間イタリアに留学。昨春、大学院を修了した時には、プロで生きていくことに迷いはなく、今では「24時間、歌のことを考えている」という。
バリトンからスタートし、大学3年次にテノールに転向。ヴェルディの作品は、
「イタリアで指揮者に“ヴェルディも歌える”と言われ、少しずつレパートリーに。留学中『シモン・ボッカネグラ』と『ラ・トラヴィアータ』を、大学院の修了公演で『運命の力』を歌いました」
そして、いきなりの主役デビューである。
「うれしいです。ミラノのヴェルディ音楽院では、スカラ座で教えている先生からも薫陶を受け、ヴェルディの精神を惜しみなく注がれました」
インタビューは『ホフマン物語』の稽古期間中。ナタナエル役と同時に、ホフマン役である福井敬、樋口達哉のカバーをつとめている。
「テノールの役は、途中から転向したこともあって、経験的にも知らないことが多い。ホフマンのカバーで全曲勉強しながら、想像以上に大変な役なんだな、と思ったり、その役の重みを学んだりと、貴重な経験をさせていただいています」
そして、クラリネットでピットに入ったこともある山本さんの将来の夢は、
「『トスカ』のうねるような音楽が魅力で、いずれカヴァラドッシを歌ってみたいし、ワーグナーにもいつか挑戦したいですね」
ともあれ、今は若きカルロに夢一杯の、若き山本さんである。
「史実ではカルロは23歳。人が成長する過程の中での、かなり近い心境で歌えると思います。自分がカルロと似ているとは思いませんが、身近な幸せを失うということも経験している。カルロならではの“孤独”があると思いますが、うまく自分なりに描きたい。そしてほかのキャストとのやり取りの中で、その孤独をハッキリ出せたらいいですね」
『ドン・カルロ』はカトリックの信仰が一つの軸になるが、山本さんは幼少時から教会は日常という環境で育ったという。若さ、恵まれた容姿に信仰への共感もあって、等身大の王子が現出することだろう。