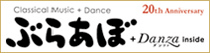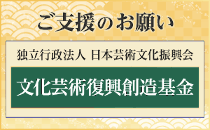語れない時代のオペラ
長木誠司
|
こ
とばと音楽の優劣を競うという発想は、きわめてヨーロッパ的なものである。それはヘレニズムとヘブライズムが交錯し、融合した文化ならではのものだからである。遠く古代ギリシャの昔、ことばと音楽は未分化の状態で仲良く暮らしていた。歌うように語り、語るように歌うことは、ニーチェ流に解釈するならば、「音楽の精神からの悲劇の誕生」をもたらした。このギリシャ悲劇を復興しようという、大それたルネッサンス的発想から、ヨーロッパのオペラ文化は誕生し、バロックの華麗な音楽環境を創り上げた。だから、そもそもオペラの根には、ことばと音楽が理想的に融合したアルカディア世界が夢見られていたと言ってもよいだろう。 シュトラウスが《カプリッチョ》で描いたことばと音楽の間の論戦は、直接的には、歌詞にも登場するグルックとピッチンニの歴史的論争を背景にし、また《ナクソス島のアリアドネ》同様に、サリエーリのオペラ《まずは音楽、それからことば》にいくつかのプロットを負っている。しかし、ここに描かれたことばと音楽の、あまりにも古典的な二項対立は、すでにそうした古典的世界、すなわち「昨日の世界」が終焉を迎えようとしている最後の灯火であるかのようだ。終わろうとしているのはほかでもない、オペラの歴史そのものであり、またそれを支えてきた社会と文化─あるいは国家と呼んでもよい─そのものである。1942年という荒々しい時代に、なんとまあ呑気な題材を、それもまた呑気なオペラなどというジャンルで、という見方が一方にあろう。しかしながら、ここではオペラそのものが古典的論争を含め、あるいは実際にパロディとして演じられるイタリア・オペラ的な場面もろとも、全面的にパロディ化されているのである。そして、ではどんなオペラを創ろうか、とみなが問いかける場面になると伯爵の一言で、その日の論争をオペラにしようという結論になってしまう。ここでは、オペラのストーリーなんていつも同じようなものの繰り返しさ、という月並みな皮肉を越えて、すでにオペラ自体が自己言及的な繰り返ししかできなくなっているという無残な姿を晒すことになっている。 《カプリッチョ》は、空虚に近いまでに美しい音楽や聴き手をおちょくったような内容とは裏腹に、実に残酷なオペラである。それは、ひとつの政治的・文化的な黄昏の時代にあって、その黄昏自体を体現するオペラなのである。ちょうどシュトラウスが《ばらの騎士》で、ハプスブルクという「昨日の世界」の黄昏を甘酸っぱく描いたように、ここで彼は自分自身の帰属する世界の黄昏を、自分を塗り込みながら描いてしまっているのである。しかしながら、この作曲家がそれでも幸せな晩年を生きていたと思われるのは、ことばと音楽という古典的なテーマを扱う「ことばと音楽」自体の有効性を、まだ彼がリニアな物語展開を伴うオペラとして実現できるという最終的な信憑を捨て切れていないことによっている。それを捨て去っていたならば、《カプリッチョ》というオペラ自体が生まれなかったはずだから(「おお、ことばよ、我に欠けたるは汝なり」という、歌にならないシュプレヒシュティンメの台詞を最後に、リニアな物語を破綻させてしまったシェーンベルクは、こうした信憑をもはや持っていなかったろう)。そして、そうした世界の崩壊後に、そうした信憑すらも失った末に書かれた、例えばマウリシオ・カーゲルの《国立劇場》のような作品の、ほんの一歩手前にまでシュトラウスは来ていたことになろう。  上:東京オペラ・プロデュース第70回定期公演「カプリッチォ」 2004年3月19日・20日 於:なかのZERO大ホール、 上:東京オペラ・プロデュース第70回定期公演「カプリッチォ」 2004年3月19日・20日 於:なかのZERO大ホール、右:クレメンス・クラウスが音楽総監督を務めた現在のバイエルン州立歌劇場客席(撮影:N・Y) |
| 長木誠司 (ちょうき・せいじ) ◎昭和33年福岡生まれ。現代の音楽、両大戦間の日本の洋楽、および18〜21世紀のオペラを研究。東邦音楽大学助教授、東京大学准教授を経て、現在東京大学教授(表象文化論)、音楽評論家。著書に『前衛音楽の漂流者たち〜もう一つの音楽的近代』、『フェッルッチョ・ブゾーニ〜オペラの未来』、『日本戦後音楽史上・下』(共著)など。 |