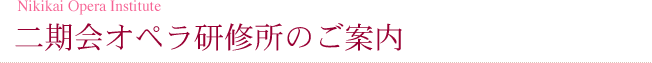2023年度 特待生レポート [前期]

中川郁文(なかがわ いくみ)
第67期マスタークラス(岩森美里クラス)
私が研修所に所属した理由は、この機関の優れた教育体制と評判に魅了されたからです。優秀な指導者と刺激的な学習環境に身を置くことで、自分の新しい可能性を引き出すこと、そして今後日本で歌手活動をしていくためにその市場を知り、先輩方の姿を近くで見て学びたいと考えたからです。
クラスの講師陣は優れた舞台のエキスパートであり、先生方のご指導のもと、自分では気づけない角度からのご指摘や深い知識を得ることができます。
クラス全体の雰囲気は非常にアットホームで、多様なバックグラウンドを持つ研修生が在籍しています。皆さん切磋琢磨しながらも協力的で支え合う雰囲気があり、学び合いの環境が整っています。
前期では作曲家ごとの演奏様式を学びながら、言語によって違う響きと音楽の関連性を知り、オペラ中のワンシーンを完成させることを目指しました。授業に臨む際には歌詞の内容理解はもちろん、ト書きの意図、歴史的背景の知識は当たり前とされ、その上で創造性をもってオペラの一場面を作り上げることを求められました。重唱ですので他の研修生との共同制作でしたが、昨今の状況により様々な制限がある中でそれぞれが工夫し努力し合いました。
私はリヒャルト・シュトラウス作曲のオペラ『アラベラ』から表題役を演じました。妹ズデンカとの二重唱です。まず、シュトラウスの独創的で甘美な音楽表現に魅了されるところから始まりました。昨年私は同作曲家の「4つの最後の歌」を歌いましたが、彼の豊かな旋律とオーケストレーションの技巧は、物語の深層に迫る感情を伝える力強いパワーがあります。しかし取り巻く美しさとは裏腹に譜読みは非常に困難で、リズムも音も自分のものにするのに大変時間がかかりました。今回オペラ『アラベラ』が持つテーマには、個人の欲望と社会の制約との葛藤が描かれています。このテーマを通して、自己と他者、現実と理想との対立を、音楽を持って表現することに努めました。登場人物の心情を理解し、彼らが歌に込める感情や思いを深く咀嚼することで、演奏や演技によりリアリティを持たせることが重要であると認識しました。
前期の授業を通して、私は授業過程においてアイデアの形成と具現化のスキルが向上したと感じています。また、批評やフィードバックを通じて、より洗練された舞台表現ができたのではないかと思っています。
研修生としての勉強を通じて、専門的な技術や理論を習得するだけでなく、自らの表現をより深化させることが叶ったと感じました。
今後挑戦したいことは、今あるスキルをいい意味で打ち破ることです。数値化されない音楽は人の耳や感性によって評価されるものですが、成長の力になってくださる先生方のお言葉を信じ、更にテクニックを磨き追求したいと思います。
以上が私の前期のレポートになります。引き続きこの機関で学び、研修所の皆さんと協力しながら成長していくことを楽しみにしています。

植田雅朗(うえた まさあき)
第67期マスタークラス(岩森美里クラス)
二期会マスタークラスの特待生として入所した経緯や、前期の内容、授業での学びについて触れていきたいと思います。
現在、東京藝術大学の大学院に修士3年として通いながら、マスタークラスの授業を受けております。大学院と同時に研修所に在籍している理由は、大きく以下の2つです。
(1) 大学院で自分が触れたことがなかった作品に触れることができること。
(2) 自分が将来オペラの舞台に立つことを目指すにあたり「今の自分にできること・足りないこと・舞台に立つ上で大切なこと」を見つけ、会得すること。
マスタークラスの前期カリキュラムは「ドイツオペラ・フランスオペラ・近現代の英・米のオペラ作品を取り上げる。」です。私はニコライ作曲『ウィンザーの陽気な女房たち』からフルート氏とその夫人の二重唱場面、そしてメノッティ作曲『電話』の後半部分という2つの場面を課題として頂きました。とくにメノッティは、全く触れたことのないアメリカのオペラで、歌う上での英語の発音が自分にはとても難しく、発声とリンクさせていくことに時間を費やしました。授業のたびに先生方や原語指導の先生からたくさんのアドバイスを頂戴し、微々たる変化を言葉にしてくださいました。それを消化し、地道な作業を繰り返すことで、少しずつ自分のものにしていくことができました。
そして今回の課題は、どちらも喜歌劇にあたる作品で、譜面の中には台詞以外の登場人物に対しての演出(ト書き)が多く、事細かに書かれています。もちろん、それを歌い手が再現しただけではオペラは成り立ちません。譜面に書いてあることや原作だけでなく、オペラが作曲され初演がなされた時代の文化や人々の習慣などを元に、作品のなかで起こっていることを捉え舞台に反映する。それだけでなく、その人物が何に対して反応し、何を思ったかをわかりやすく見せる。これが「舞台に立つ上で大切なこと」の1つだと私は思います。そしてこの一連の過程を全て繋げてやり切ることは、今の自分にとってとても難しいことですが、演出の先生にたくさんの叱咤激励をいただいたことで、少しずつ自分の意識や舞台上での所作に変化が見られました。
冒頭で大学院と同時に研修所に在籍していると述べましたが、研修所で得た課題やいただいたアドバイスを大学院で実践することで、常に新しい発見があります。
まだ分からないことばかりですが、この環境を最大限に活用し、マスタークラスでの学びを確実に自分のものにしながら、今度とも精進いたします。

大澤桃佳(おおさわ ももか)
第68期本科(宮本益光クラス)
私は、今年度より特待生として本科に入所し勉強させていただいております。
昨年までは東京藝術大学大学院の声楽専攻に所属しており、大学院在学中にオペラを学ぶ機会が少なかったため、こちらのオペラ研修所の受験を決めました。
現役でご活躍されている素晴らしい先生方から、歌のことはもちろん、役作りのことや音楽との向き合い方、プロの音楽家としての姿勢や心構えなどを直接ご指導いただくことができ、充実した時間を過ごさせていただいております。声種の違う声楽の先生方、ピアニストの先生方、演出の先生、指揮者の先生、所作指導の先生、それぞれの立場からアドバイスをくださるので、多角的な視点で自分の声や演技と向き合うことができます。
本科前期のカリキュラムでは、邦人作品に取り組みました。私は團伊玖磨作曲『夕鶴』のつうを演じました。前期の初めに、所作の先生から着付けと基本的な所作を学び、それからは毎回の授業で、自分で和服の着付けを行い、授業を受けました。慣れない着付けで戸惑いながらも、同期の仲間と協力し合いながら少しずつ上手く着付けられるようになったと思います。
着慣れない和服での音楽稽古は、いつものようにブレスを吸えず、立ち方や支えの位置などに悩み、とても苦戦しました。立ち稽古が始まってからも、正しい所作を意識して動きながら、歌の表現や発声のことも考え、頭を常にフル回転していました。
本当に大変でたくさん悩みましたが、それ以上に、できないことに挑戦し続けるエネルギーや知らない世界に触れられる高揚感で満ち溢れていて、毎回の稽古が楽しみで仕方ありませんでした。
前期のまとめの邦人作品チェックでは、今できる精一杯を尽くし、つうを生きることができたと思います。
入所したての授業の初めに、宮本益光先生が「授業では、歌っている時間より圧倒的に座っている時間が多い。その時間をどう過ごすかはそれぞれ次第だ」という風におっしゃっていました。自分が前で歌っている時はもちろん多くの学びがありますが、聴講時間も勉強や気づきの連続です。先生方のアドバイスで、同期の歌や表現がどんどん良い方向に変わっていくことに刺激を受け、私がこの役を演じるのならこの部分はどんな表現をするだろう。今の先生のアドバイスは自分にも当てはまるから今度試してみよう。などと考えながら聴いていると、あっという間に時間が過ぎていきます。
限られた時間の中で、どれだけ多くを学び吸収できるかは自分次第です。これからも、自分の課題と真摯に向き合い、仲間とお互いを高め合いながら充実した時間を過ごせるように頑張りたいと思います。

村田 涼(むらた りょう)
第68期本科(宮本益光クラス)
私は2022年3月に洗足学園音楽大学大学院を修了し、今年度本科特待生として入所いたしました。大学院修了後1年間は、仕事をしながら日々の研究や練習に励んでおりましたが、入所後も同じペースで仕事を続けていくことに対して、体力的、経済的に不安を感じておりました。そのようななか、特待生に選んでいただいたことで、自分の声や音楽に集中して向き合い、充実した研修生活を送ることができています。
研修所では、将来オペラ歌手になるために必要なことを、舞台経験が豊富な先生方が丁寧に教えてくださいます。私が所属している宮本益光先生のクラスでは、実際の歌唱におけるテクニックだけでなく、曲への向き合い方やオペラのキャラクターを演じる際の心構え、歌で表現することの本質や歌い手として心にとめておくべき大切なことなど、新しい学びが多くあります。なかでも、先生方がオペラの現場で感じられた様々な気付きを、私たち研修生に惜しみなく共有してくださることは、本当に得難い経験だと感じています。このような素晴らしい学びを得られる環境に感謝し、実践に取り入れ、活かしていけるよう精進したいと日々感じております。
さて、本科では、前期の半分の期間を使って邦人作品に取り組みました。初回の授業で集中的に所作の基礎を学び、音楽稽古期間を経て、演技表現に応用しました。慣れない和物所作にかなり苦戦しましたが、伊奈山明子先生から徹底した所作指導を受け、少しずつ体になじんできました。足の運び、立ち方、体の支え方、一つ一つが初めての体験で、感覚をつかむために、授業外の日々の生活のなかでも所作や体の使い方を意識して過ごしてみるなど、とにかく何度も練習しました。それでも、音楽のことや演技のことにも気を配りながら実践するのはなかなか難しく、納得のいくところまで仕上げていくのは大変な作業でした。また、所作以外にも、日本語の作品に取り組むにあたり、改めて日本語の特徴について考え、言葉のさばき方を研究しました。これまでに日本歌曲に取り組んだときと同様、母国語であるからこそ、無意識に普段話しているときと同じポジションで歌ってしまったり、舞台で響かせるには浅すぎてはっきり聞こえない、ニュアンスも伝わりにくい歌唱になってしまったりしがちでした。こういったことに向き合い、母国語をより美しく歌うことを目指して研究したこの期間は、私にとって大変有意義なものになりました。
前期の後半では、ベルカント作品に取り組みます。オペラの基礎や声と向き合う貴重な機会ですので、しっかりと精進してまいりたいと思います。
4月に入所してから今まで、あっという間に過ぎたように感じるのは、次々と新しい学びや発見があり、それを一つでも多く深く理解し実践しようしてきたからだと思います。これからも貴重な時間を無駄にすることなく、貪欲に学び続けることで、自らの成長につながる充実した1年にしたいと考えております。

栁澤玖紀(やなぎさわ たまき)
第69期予科(萩原 潤クラス)
私は現在、二期会オペラ研修所69期予科夜クラスに在籍しています。
まず、私が二期会オペラ研修所を受験した理由は、現役で活躍されている声楽の先生方からご指導いただけること、演技を演出家からご指導いただけること、試演会やソロ試験、コンサート等の本番の機会が多くあること、そしてオペラの舞台に立ちたいという同じ志を持った仲間に出会い、共に学ぶことが出来るからです。
私の在籍している夜クラスは、主任の萩原潤先生をはじめとする、それぞれの声種の素晴らしい先生方が、研修生一人一人に愛情深く、丁寧にご指導くださいます。クラスメイトは経歴や年齢も様々ですが、明るくとても良い雰囲気で、互いに学びあう環境が整っていると感じます。
予科の前期カリキュラムは、モーツァルトのオペラ作品『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』から、レチタティーヴォ・セッコを含む重唱に取り組みます。私は前期、『フィガロの結婚』からスザンナとケルビーノの二重唱場面と、『コジ・ファン・トゥッテ』からドラベッラとグリエルモの二重唱場面に取り組みました。
私はこれまでに演技の経験がほとんどなかったため、演じる役の感情を途切れることなく、分かりやすく伝わるように演技することの難しさを実感しました。先生方からオペラの役を演じる際の心構えや、効果的な音楽の表現の仕方、演じ方など様々ことを丁寧にご指導いただきました。特に演技では、感情を頭で考えて内向きな表現をするのではなく、客席に向けて最大限の表現をすること、そして演じている自分自身がその状況をなにより楽しむことの大切さを学びました。
前期はいただいた役とも自分自身とも向き合う時間を大切に勉強に励みました。また自分にない素敵なものを持ち、それぞれ違う課題と向き合うクラスメイトのレッスンを聴講できることは、私にとって沢山の気づきや学びがあり貴重な時間となっています。
後期は、引き続き前期に取り組んだモーツァルトのオペラ作品に加えて、『魔笛』にも取り組みます。初めてドイツ語のオペラ作品に取り組むのでとても楽しみです。

及川泰生(おいかわ たいせい)
第69期予科(萩原 潤クラス)
私は現在、東京藝術大学の大学院に修士1年生として通いながら、二期会研修所予科の授業を受けております。私は音楽大学出身ではなく、オペラアリアは勉強したことがあっても、実際にオペラを経験したことはありませんでした。しかし、将来的にオペラを歌ってみたいという思いがあり、一からオペラを勉強するため二期会研修所の予科に通うことを決めました。
予科の前期では、モーツァルトのオペラ作品に取り組みました。具体的な作品としては、『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』の3作品で、私は『フィガロの結婚』のアルマヴィーヴァ伯爵、『コジ・ファン・トゥッテ』のグリエルモの役を勉強しました。前期の4~5月は音楽稽古を行い、6月から立ち稽古に入りました。
初めての演技に最初はとても戸惑い大変でしたが、先生方のアドバイスを聞き、自分なりに試行錯誤して過ごしました。先生方は、音楽的な部分や演技的な部分に加え、自分はどのように見えているのか、その役を演ずるために何が足りていないのかなど、様々な角度からいつも優しく丁寧なアドバイスを頂きました。その中でも特に大切にしている言葉は、主任の萩原先生が授業の中で何度も話された「感情を作る」という言葉です。演技の中で先生から言われた動作を受動的に行うだけではなく、登場人物の心情やその状況を具体的にイメージし、その感情を自分の中に生み出すことによって自発的で自然な演技になることを、自分自身の経験として、また他の研修生の様子を見て強く実感しました。感情が作れたときと、そうでないときの違いを少しずつ自分で認識できるようになり、講師の先生方のアドバイスが最初の頃と比べてより深く理解できるようになったのかと思います。
そして、感情を作るために演出の今井先生が様々な角度から研修生にアプローチしてくださりました。特に印象的だったのは、私が『フィガロの結婚』1~2番のフィガロをカヴァーで歌った際、「登場の時に、結婚の喜びを台詞は何でも良いから、大きい声で表現してみて」と言われ、やってみると本当に嬉しく幸せな気持ちになり、体が高揚していく感覚が生まれてきたことです。身振り手振りで感情を表現するだけではなく、実際に自分がその感情になった時に生まれるエネルギーの大きさを強く感じ、萩原先生が言っていた感情を作るとはこういうことなのかもしれないと思った、とても印象的な瞬間でした。
研修所で勉強を始めてから、改めてオペラを見ると歌手の立ち姿や歩き方、感情表現の豊富さなど、今まで気づかなかったことが見えるようになり、よりオペラの面白さ、オペラ歌手の皆様の素晴らしさを理解することができるようになりました。
オペラ歌手育成支援
―― 世界で活躍する声楽家を育成するため皆様からのご支援をお願いいたします。
■オペラ歌手育成会〈年会員〉
一口 個人10万円 法人20万円
・利用目的:研修生奨学金への充当、研修所運営費への充当
| ・御礼内容: | 二期会オペラ研修所コンサート、二期会新進声楽家コンサートへのご案内 二期会オペラ研修所コンサート、二期会オペラ研修所マスタークラス修了試演会 各プログラムへのご芳名の掲載、ホームページへのご芳名の掲載 |
■ヤング・シンガーズ・サポート〈オペラ歌手育成寄付〉
一口1,000円・3口以上
・利用目的:研修生奨学金への充当、研修所運営費への充当
・御礼内容:二期会オペラ研修所コンサート、二期会オペラ研修所マスタークラス修了試演会
各プログラムへのご芳名の掲載(1万円以上ご寄付の方)
ホームページへのご芳名の掲載(1万円以上ご寄付の方)
▼「オペラ歌手育成支援」に関する詳しいご案内とお申込方法はこちらをご覧ください
・【基金・ご支援ガイドブック】
ご支援はインターネットからのクレジットカード払いでもご寄付いただけます
▼東京二期会では上記の他にもさまざまな事業目的に対するご支援をお願いしております
詳しくはこちらをご覧ください
・東京二期会へご支援のお願い