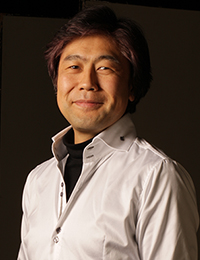小森 輝彦
満を持して挑む、バリトン冥利に尽きる大役
文=広瀬大介
写真=福水託
17年におよぶドイツ滞在、そして12年におよぶゲラ・アルテンブルク歌劇場での歌手生活。地元の誰からも愛される存在となった小森輝彦には、“宮廷歌手”という最高の名誉が授けられた。そんな小森が現地で認められるきっかけとなったのが、同劇場で初めて歌ったヴェルディの『リゴレット』タイトルロールだったという。
「先方がまさに『リゴレット』を歌える歌手を探していて、僕はドイツの専属歌手になるという夢が叶ったのです。ゲラも、アルテンブルクも、どちらの劇場も客席数が600席と小さいので、観客の反応はダイレクトに伝わってきます。カーテンコールのとき、自分だけに称賛の足踏みをしてくれた時は感激しました。小さい街ですから、通りを歩いていると、知らない人でも気さくに声をかけてくれます。でも、舞台を通じてお客さんと交流できたことがやはり嬉しいです。宮廷歌手という称号の授与に明確な基準はないのですが、ひとつの都市にじっくり腰を落ち着けて活躍し、芸術的功績とパーソナリティによって、その劇場のレベルアップに貢献したひとに与えられる、ということのようです。誰にも告げたことはなく密かな目標だったので、実現したときは驚きました(笑)」
明るく、力強いハイ・バリトンという小森の声質には、今回の『マクベス』タイトルロールをはじめとするヴェルディの諸役がうってつけである。
「僕のボイス・トレーナーは、前々からそう主張していました。ドイツに縁が深いのでドイツ系、と思われがちですが、僕は※ウバルド・ガルディーニ先生の薫陶をみっちりと受けた世代なので、イタリアオペラには強い愛着があります。その中でもドラマ作者として最高なのはやはりヴェルディですから、ナブッコ、ジェルモン、ヤーゴなどを歌った経験が生きると思います。
マクベスはバリトン冥利に尽きる役ですね。この人の煩悩と狂気をめぐって周りの人々が踊らされるので、役に“色”がないと全体が色褪せてしまう。責任重大だと思います。人間的な弱さを見せられる役、というのが、僕には魅力的です。コンヴィチュニーさんとの仕事は今回が初めてです。ドイツの劇場に行く前は“演出家からの要求が甚だしい国らしい”と聞かされて怯えていました(笑)。でも、彼らの演出どおりに動いたとしても、結局は舞台の上では“僕の”役でしかありえないんだな、と気付いたら、とても楽になりました」
ドイツ語の明晰さで高い評価を得た小森。歌手としての将来像も明瞭にもちあわせている。
「子音を際立たせなかったら絶対に歌えないドイツ語、子音を歌いすぎると怒られるイタリア語、それぞれに違いがあります。ベルカントの神髄は“いかにアクセントを避けるか”ですからね。いわば、歌とは子音、母音、子音、母音と紡いで行く「織物」です。さまざまな言語・文化を受け止め、作品を深く読み込むための「器」を自らのうちに作っていかなくてはなりません。生きた言葉が作曲家に霊感を与え、その結果生まれた音楽を歌うわけですから、言葉がキチンと届くような仕事をしたい。お客様に“訳を見なくても意味がわかるような気がした”と言っていただいたことがあるのですが、これは、僕にとっての勲章なのです。
今後歌いたい役ですか? ヴォータンやスカルピアはまた歌いたいです。ヴェルディなら『ファルスタッフ』のフォードやファルスタッフ、『仮面舞踏会』のレナート。『ドン・カルロ』のロドリーゴなどでしょうか。でもガルディーニ先生は“『ドン・カルロ』はフランス語に付曲されたものだからフランス語で歌え”と言われていましたね(笑)」
※ウバルド・ガルディーニ Ubaldo Gardini イタリア・ボローニャ生。1963年より英国コヴェント・ガーデン等で名コーチとして活躍し、コリン・デイヴィスの片腕ともいわれた。1981年メトロポリタン・オペラ劇場にて副指揮者・コーチをつとめる。1984年より、東京芸術大学オペラ科客員教授に着任、イタリアオペラ、ディクションコーチとして、多くのオペラ歌手を育てた。二期会では1998年新国立劇場『フィガロの結婚』上演に際し、演出・舞台美術として携わり、二期会オペラ研修所でも指導にあたった。2011年11月24日イタリアの病院にて永眠。
今井 俊輔
メカニカルに鍛えた合理的な発声は、
本場の味わい
文=香原斗志
写真=福水託
マクベスのタイトルロールは、すでに2回歌っている今井さん。
「イタリアの先生からヴェルディ作品に取り組むように言われ、ヴェルディ歌手として進んで行こうと。とくにマクベスは、残忍さの表現などがストレートすぎるほど切れ味よく、一瞬で感情を表すのが難しいですね」
と語るように、志がハッキリしているが、歌手になるまでに意外な紆余曲折をへている。
「音楽は4歳のころ、しつけとしてピアノを習わされていたくらいで、その後は水泳に明け暮れていました。国立音大に進んだのも、水泳以外のことをしたかっただけで、ほかには獣医大を受けたんです。ただ、国立音大の音楽教育科は各分野をまんべんなく学ぶのですが、僕はひとつを究めるほうが好き。マーラーの千人交響曲ですごい歌手を聴いて、こういうのをやりたいと思ったのを機に、東京芸大声楽科を受け直したんです」
いま、イタリア作品ばかりをレパートリーにしているが、芸大に入るまではイタリアオペラどころか、オペラ自体をほとんど知らなかったという今井さん。声楽を習ううちに、実は水泳少年のころの経験が役に立つことがわかったという。
「水泳をやっていたころ、筋肉の動き方に興味があったのですが、声楽でも先生方からいろんな筋肉の動きを教わって、結構スポーティなんだということがわかり、それが自分の中ですごくヒットしました」
だから、発声のシステムをメカニカルに解析でき、合理的に声を出せるのだろう。往年の大バリトン歌手、ピエロ・カップッチッリが大好きだそうで、
「彼は潜水士だったときがあるそうで、ブレスが驚異的に長かった。そして口を使う際のやわらかさをはじめ、筋肉の動きがコントロールできていて、歌うラインを崩さないで歌い続けることができました。目指したいな、と思いますね」
“水つながり”もあるのだから、ぜひ目指してほしいものだ。また、70歳になってなお、世界の第一線でヴェルディを歌い続けるレオ・ヌッチについても、
「僕も絶対、70歳まで第一線で歌っていたいと思いますが、ヌッチが長く歌えているのは、身体をメカニカルに動かし、機能的に外れたところがなかったからではないか。日本人は歌を感覚や精神性で理解しがちで、それも大事ですが、イタリアの名歌手たちは発声を理論的に理解していますね」
もちろん、カップッチッリとヌッチのマクベスも聴いて研究しているという今井さん。『マクベス』にはヴェルディ作品の中でも珍しいほど、さまざまな試みがなされている、と語る。
「演劇的にも好きですが、音楽による場面構成がすごい。マクベスが夜、ダンカン王を暗殺しようとしている場面ですが、ナイフが出てくるけど、幻影だからつかめない。そのとき王の殺害が自分の意志だと決意して、急に“星よ、俺の残忍さを隠してくれ”と。人を殺しに行こうとしているのに、英雄的になるんです。そこに夫人がきて、続いて王を殺し終えたマクベスが入ってきて、“お前にはもう安らぎはないぞ”と動揺する。こうした場面が、ヴェルディの音楽の流れのなかですべて表現されているんです」
そんな作品を、これまではオーソドックスな舞台で歌ってきたそうだが、今回の演出家は鬼才、コンヴィチュニー。
「今からワクワクしていますよ。エンターテインメント性が高い、観る人が楽しめる舞台になるといいですね」
深く、風格のある声をもつ今井さんだが、暇なときは、
「寝ています。夕方の5時に寝て、次の日の5時に起きたなんてこともありました」
イタリアを思わせる、この独特の大らかさが、切れ味のよい悲劇にどんな味わいを加えるのか、楽しみである。