文:編集部 写真:広瀬克昭

オペラだけでなく、ミュージカル、演劇、芝居など幅広い分野において、役柄に沿いかつ美しい衣裳を創出することで定評のある前田文子さん。
2010年2月白井晃演出『オテロ』の他、11月『メリー・ウィドー』、11年4月『フィガロの結婚』の再演が決定している。
総合芸術製作の一翼として、類稀なる才能を発揮している彼女の、オペラへの思い、注ぐ情熱について、二期会会員バリトン宮本益光と共に語っていただいた。
“表”と“裏”の二つの異なる角度から、ひとつの美しい舞台を支えることの魅力とは。
デザイナーに至った経緯について
宮本 いろいろとお聞きしたいことはあるんですけど、まずきっかけから始めたいんですが、小さい頃からお姫様の絵とか描いていたんですか? 衣裳のデザイン画もご自分で描くんですよね。あれがね、すごく素敵なんですね!
前田 ありがとうございます。昔から絵は好きだったけど、これが職業になるなんてちっとも思ってなかったです。普通に結婚してお嫁にいきなさい、と育てられたから。
宮本 なるほど。ご出身はどちらですか?
前田 北海道の洞爺湖のすぐ傍です。それまでお芝居にも全然興味なかったんですけど、高校三年生の卒業する間際の春休みに、演劇を観て「面白い!!」と思ったの。
宮本 それは何の演目だったんですか?
前田 私の大好きな三田和代さんが演じていた「オンディーヌ」というジロドゥの作品です。実は三田さんとはアシスタント時代から、今までもう何度かお会いしているのに、全然そのことが言えなくて。
宮本 畏れ多くて?
前田 はい。やっと5、6年前のお仕事で「実はこうで…」とお話しました。
宮本 それで、大学に入ってからは?
前田 大学に行っても、演劇は趣味でやろうと思って、演劇部に入ったの。学生演劇だと、表に出つつ裏方も担うじゃない?
宮本 え、じゃあ、表にも出つつ?
前田 そうです。最初に先輩が演出した作品に3、4本出てから表の出演は辞めましたね。衣裳を始めたら、そっちが面白くなってしまって。その面白さは要するに役者をやるのと感覚が一緒というか、役者よりももっとたくさんの役になれるという感覚なんです。

デザイナー・ 前田文子のこだわり
前田 最近よく思うんですけど、自分の変身願望がものすごく強いせいか、固定的スタイルを決めたくないんです。コスチュームで表現することを、すごく楽しいなと思います。でも、作品を観たみなさんに、よく「前田さんらしくて素敵ですね」と言われます。それは、タヌキのしっぽみたいに化けきれないで出ちゃう部分を、みなさんが“らしい”と言ってくれていると思うんです。
宮本 でも確かにそうなんだよね。「(『フィガロの結婚』の)アルマヴィーヴァだから衣裳はこうです」って説明されてもね。その個性がないんだったら、誰がやっても同じ衣裳になりかねないし。
前田 そう! そうなんですけれど、自分の中では精一杯、アルマヴィーヴァであるべしと思って、デザインをやっているわけ。役者さんで言えば「すごい、この人は本当にアルマヴィーヴァだった」と評価されることと、「やっぱり○○さんが演じるアルマヴィーヴァだから、イイ」と言われることのどちらが大事なのかと同じです。私は観る側としては、演じている役者さんの個性が消えちゃって、キャラクターになりきっている方が、無垢に楽しめて素敵だと思います。だから“らしい”と言われても「こんなになりきったのに、なんで“らしい”の!?」って。
宮本 そっかそっか(笑)。
前田 だから結局、なりきろうとしても出ちゃうものは出ちゃう。だったらそれはしっぽの範囲にとどめておきたい。しっぽ以外の部分までお客様に見えてしまったら低俗となる危険があるし、同時に、その役になりきれていないコスチュームを提供したことがプロとしてどうなのでしょう? 本当に自分が意識して「今回はがんばった」と思える衣裳を作った時は、例えばそれが宮本さんの(『欲望という名の電車』の)スタンリーの衣裳だったら、スタンリーが褒められればいい。「スタンリーの着てたあの赤いシャツがよかったです」と褒められた時はデザイナーとしてはダメだなと思うわけ。
宮本 なるほどね。それは面白い視点だな。でも真実ですね。

宮本 スタッフと歌手は、一緒に仕事をしていてもやっぱり距離がありますよね。でも僕たちと同じように台本を読みくだいて、その中で役の人格が衣裳に反映されているんですよね。前田さんの衣裳やデザイン画を見る時は、自分が稽古を重ねてきて、役に近づいている段階です。それを見て役作りの上ですごく助けられたり、逆に「そうきますか」と奮起させられたり。そこがきっと舞台の共同作業の魅力なんだろうな。
前田 演出あってのことですから、私のアイデアがいつも100%ではないんです。この前の『鹿鳴館』(2010年6月新国立劇場・鵜山仁演出)の、モノトーンでどこか荒廃した感じにしてもそうです。そういう演出プランをいただいたらそこを楽しむというか、私なりのアイデアを含めながら、なぜこういう世界観なのかを伺って、更に演出に沿っていきます。やはりそこは演出が絶対だから。
宮本 ということは、演出家としての視点も、前田さんは持っているということですね?
前田 そうとも言えます。でないと演出家とお話できないでしょう。
宮本 僕は個人のプライドとして、舞台に立たせてもらっていることで、スタッフに依存しすぎてはいけない、と強く思っています。前田さんは、衣裳デザイナーとして、作品とその中のすべての役と向かい合っているから、僕らよりも何倍ものエネルギーが必要だと思う。でも数役の人生を衣裳で表出していく意味では、やはり演技者ですよね。だからこそ「あなたのおかげで舞台に立たせてもらっている」というより、“共演者”だと思う。それは照明や演出の人も同じで、ある一つの作品に全員で向かい合い、創り上げるための“同志”なんですよね。
前田 私たちは縁の下の力持ちだけではないんですよね。もちろん本当に支えているところはあるけど、そちらに委ねてお願いしているところも多くあります。衣裳だけは役者さんに着てもらって初めて生きるのですから「衣裳のためにも素敵に着てね」という感覚でしょうか。逆にキレイにさばいて素敵に着てくれたら、もうそれだけで感謝です。
宮本 そういえば「これは俺の服でしょう」と嫉妬のまなざしで舞台を観続けたのは、前田さんの『ドン・ジョヴァンニ』(尼崎アルカイックホール・岩田達宗演出)の衣裳。あれが最初ですね。あれを自分こそ着たいと思った感情。
前田 私もやっぱり、自分の着たい服を(舞台に)乗せようと思うから。役者さんと同じですよ。「もし私が浮浪者の役だったらこういうのが着たいの!」という思い。だから汚す時も精魂込めてやります。ただ美しく作るのではなくて、その役になるにはどうしたらいいかという美意識です。だから毎回楽しいのでしょうか。
前田文子(まえだ・あやこ) 衣裳デザイナー
1988年より緒方規矩子氏に師事。舞台衣裳デザインを学ぶと同時にアシスタントを務める。88年度文化庁在外研修員として渡英。95年度伊藤熹朔賞新人賞、02年度読売演劇大賞優秀スタッフ賞、03年度伊藤熹朔賞本賞、05年度橘秋子賞クリエイティブスタッフ賞。主な作品に宮本亜門演出『フィガロの結婚』『コジ・ファン・トゥッテ』「グレイ・ガーデンズ」、栗山民也演出『マダム・バタフライ』「炎の人」、鵜山仁演出「ヘンリー6世」など多数。
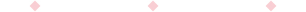
宮本益光(みやもと・ますみつ) バリトン
愛媛県出身。
東京芸術大学卒。同大学大学院修士課程修了。同大学院博士後期課程修了。2003年A.プレヴィン「欲望という名の電車」スタンリー役の好演で一躍脚光を浴び、04年二期会オペラデビューとなった宮本亜門演出『ドン・ジョヴァンニ』タイトルロールでは、新時代のドン・ジョヴァンニ像を演じ各方面より絶賛された。第61回文化庁芸術祭大賞受賞公演06年『コジ・ファン・トゥッテ』グリエルモなど。
二期会会員

![]()






